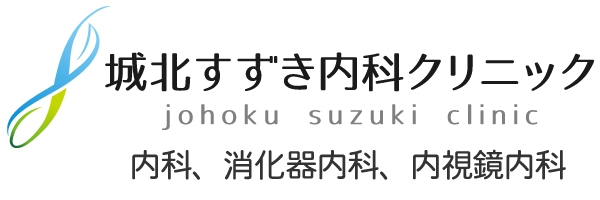胃食道逆流症(逆流性食道炎) gred
胃食道逆流症とは
胃食道逆流症(逆流性食道炎)とは
胃食道逆流症(以下GERD: Gastro-Esophageal Reflux Disease)とは、胃の中の酸(近年では、厳密には胃酸のみが原因でないことがわかってきている)が食道に逆流することで、さまざまな不快な症状を引き起こす病気のことです。代表的な症状には、胸やけ、みぞおちの痛み(上腹部痛)、吐き気、喉の痛みなどがあり、これらをまとめて「胃酸逆流症状」と呼びます。
この病気は大きく2つのタイプに分けられます。
逆流性食道炎
1つ目は、逆流性食道炎(以下RE: Reflux Esophagitis)と呼ばれるタイプです。これは内視鏡検査で、食道と胃のつなぎ目(食道胃接合部)に赤み(発赤)、ただれ(びらん)、傷(潰瘍)などの異常が見られる場合です。つまり、胃酸の逆流によって食道の粘膜に実際に傷がついている状態です。
非びらん性胃食道逆流症
2つ目は、非びらん性胃食道逆流症(以下NERD: Non-Erosive Reflux Disease)と呼ばれるタイプです。こちらは、症状はあるものの、内視鏡で見ても食道に粘膜の傷が見つからない場合です。つまり、胸やけなどの不快な症状があるにもかかわらず、食道自体には目立った損傷が確認できない状態です。
これまで、胃酸が原因となる病気は「逆流性食道炎(RE)」という名称で呼ばれることが多くありました。しかし、最近では、胃酸の逆流によって症状が出ているのに、食道に傷が見つからない非びらん性胃食道逆流症(NERD)の患者さんがむしろREに比して多いことがわかってきました。実際には、胃酸による症状がある方のうち、およそ70%がこのNERDに該当するとされています。
こうした背景から、「RE」だけでは胃酸が関係するすべての病態を説明しきれないため、「GERD」という名前が広く使われるようになりました。つまり、「GERD」は、「RE」と「NERD」の両方を含む、より広い概念の病名です。
胃食道逆流症(GERD)=逆流性食道炎(RE)+非びらん性胃食道逆流症(NERD)
現在では、医療の現場においても、胃酸の逆流による病気をまとめて「RE」と呼ぶのではなく、「GERD」と表現するのが一般的になりつつあります。
胃食道逆流症について、これまでにわかってきたこと
GERDは、主として胃酸が食道に逆流してしまい、胸やけやのどの違和感、吐き気などの症状が出る病気です。これまでの研究から、次のようなことが明らかになっています。
日本人のGERDの患者は年々増えている
その理由として、次のようなことが関係していると考えられています。
・食事の内容が欧米化したことで、胃酸が多く出る人が増えている・ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)に感染している人が減ってきている
・ピロリ菌を取り除く治療(除菌治療)が広まったことで、慢性的な胃の炎症(慢性胃炎)を持たない人が増えた
慢性胃炎がある人(≒ピロリ菌に感染している人)は胃酸の分泌が加齢とともに減少する傾向があります。一方慢性胃炎がない人(≒ピロリ菌に感染していない人)では、逆に胃酸が加齢しても活発に出るため、胃酸の逆流が起きやすくなると考えられています
ピロリ菌に感染している人では、胃食道逆流症になりにくい傾向がある
ピロリ菌に感染している人では、胃酸の分泌が減弱していることが多いため、胃酸の逆流による症状が出にくいと考えられます。
GERDの患者(特にREのタイプ)には、肥満気味の人が多い
体重が多いと、お腹の中の圧力が高くなり、それによって胃酸が食道に逆流しやすくなるためです。
GERD(特にRE)は、「食道裂孔(れっこう)ヘルニア」と深く関係している
食道裂孔ヘルニアとは、本来はお腹の中にあるはずの胃の一部が、胸の方に飛び出してしまう病気のことです。これがあると、胃と食道のつなぎ目の締りが悪くなり胃酸が逆流しやすくなります
GERDの患者さんの約70%以上は、「NERD」である
この「非びらん性胃食道逆流症」は、英語ではNERD(ナード)と呼ばれます。内視鏡で食道を見ても、傷(びらん)が見つからないタイプの胃食道逆流症です。
最近では、NERDは逆流性食道炎の「軽い症状のタイプ」ではない可能性が高いと考えられている
以前は、「NERDは逆流性食道炎の軽症」と考えられていましたが、最近の研究では、NERDと逆流性食道炎は発症のしくみが違う可能性があるとわかってきています。
REは、胃酸が食道の中に過剰に逆流し、粘膜が酸にさらされることで発症する
REの方は、胃酸の強い刺激によって、食道の内側(粘膜)が傷つき、炎症を起こしてしまいます。
REになりやすい人の特徴
以下のような人は、REになりやすいとされています。
・高齢の方
・男性
・たばこを吸う方
・精神的な病気を持っていない方
・胃酸を抑える薬が効きやすい方
・高齢の方
・男性
・たばこを吸う方
・精神的な病気を持っていない方
・胃酸を抑える薬が効きやすい方
NERDの約70%は、「胃酸への知覚過敏」が原因
NERDの方は、胃酸やほかの要因が逆流してきたときに、通常よりも強く不快に感じる「知覚過敏」が原因となっている場合が多いとされています。つまり、胃酸そのものの量が多いわけではなくても、少しの逆流でつらい症状が出てしまうのです。
NERDの約40%は、胃酸以外の原因によって起きる
NERDの40%の方では、次のような原因が考えられています。
・アルカリ性の液体(胆汁など)が逆流してくる
・空気が逆流する
・食道の動きに異常がある(食道運動異常)
こうしたNERDの方の中には、胃酸を抑える薬が効きにくい「薬に抵抗性がある」人が約40%いると考えられています。また、精神的な病気(うつや不安など)を持っている方が多いという傾向もあります。
・アルカリ性の液体(胆汁など)が逆流してくる
・空気が逆流する
・食道の動きに異常がある(食道運動異常)
こうしたNERDの方の中には、胃酸を抑える薬が効きにくい「薬に抵抗性がある」人が約40%いると考えられています。また、精神的な病気(うつや不安など)を持っている方が多いという傾向もあります。
GERDの患者さんは、生活の質(QOL)が大きく下がる
GERDによるつらい症状によって、日常生活に支障をきたすことがあります。その影響は、急性期の十二指腸潰瘍(しばらくの間強い腹痛が続く病気)と同じくらい生活の質が低下すると言われています。
このように、GERDは、さまざまな原因やタイプがあり、人によって症状の出方や治療の効き方も異なります。正確な診断と、個々の状態に合った対応がとても大切です。
胃食道逆流症の症状について
GERDには、大きく分けて2つのタイプの症状があります。「定型的な症状(食道に関係する症状)」と、「非定型的な症状(食道以外にあらわれる症状)」です。
定型的な症状(食道に関係する症状)
・胸やけ
・みぞおちの痛み・呑酸:酸っぱい胃液が口の中にこみあげてくる
・お腹の張り(腹満感)
・胃もたれ(食後に胃が重く感じる)など
これらの症状は、次のようなときに悪化しやすくなります
・食べすぎたとき
・急いで食べたとき(早食い)
・脂っこいものを食べたあと
・お酒を飲んだあとなど
・急いで食べたとき(早食い)
・脂っこいものを食べたあと
・お酒を飲んだあとなど
また、次のような体勢や状況でも症状が強くなることがあります。
・前かがみの姿勢(前屈姿勢)
・咳をしたとき
・きつい服を着てお腹を締めつけたときなど
・咳をしたとき
・きつい服を着てお腹を締めつけたときなど
しかし、水を飲むことで一時的に楽になることもあります。
非定型的な症状(食道以外にあらわれる症状)
胃酸の逆流が、食道以外の体の部分にも影響を与えることで、いろいろな症状が出ることがあります。これらは「非定型的症状」や「食道外症状」とも呼ばれます
呼吸器に関係する症状・疾患(呼吸器系)
・慢性的なせき(慢性咳嗽)
・気管支喘息
・肺炎
・気管支喘息
・肺炎
胃酸がのどや気管支の方まで上がってくることで、これらの呼吸器の症状があらわれることがあります。
耳・鼻・のどに関係する症状・疾患(耳鼻咽喉系)
・のどの違和感
・のどの痛み
・飲みこみにくさ(嚥下障害)
・声がかれる(嗄声:させい)
・副鼻腔炎
・中耳炎
・のどの痛み
・飲みこみにくさ(嚥下障害)
・声がかれる(嗄声:させい)
・副鼻腔炎
・中耳炎
これらも、胃酸が食道より上の部分に影響することで出てくると考えられています。
心臓まわりのように感じる症状・疾患(循環器系)
・胸の痛み(心臓が原因ではない「非心臓性胸痛」)
・背中の痛み
実際には心臓に問題がないにもかかわらず、胸や背中が痛むことがあります。
・背中の痛み
実際には心臓に問題がないにもかかわらず、胸や背中が痛むことがあります。
その他の症状
・歯が溶ける(歯牙酸食:しがさんしょく)
→胃酸が口の中に戻ってくることで、歯が酸にさらされて傷むことがあります。
・眠れない、睡眠の質が悪くなる(睡眠障害)
・睡眠時無呼吸過眠症候群
→寝ている間に呼吸が止まる病気で、GERDとの関わりがあるとされています。
・歯が溶ける(歯牙酸食:しがさんしょく)
→胃酸が口の中に戻ってくることで、歯が酸にさらされて傷むことがあります。
・眠れない、睡眠の質が悪くなる(睡眠障害)
・睡眠時無呼吸過眠症候群
→寝ている間に呼吸が止まる病気で、GERDとの関わりがあるとされています。
このように、GERDは胸やけなどのわかりやすい症状だけでなく、せきやのどの違和感、睡眠の問題など、一見すると関係なさそうな症状も引き起こすことがあります。どのような症状があるかを知っておくことは、早めの気づきと適切な対応につながります。
胃食道逆流症の診断について
GERDの診断は、いくつかの方法を組み合わせて行います。1つの検査だけで確定することが難しいため、総合的に判断する必要があります
問診
胃カメラ
「胃カメラ(上部消化管内視鏡)」で食道や胃の様子を確認します
胃カメラを使って、食道と胃のつなぎ目(食道胃接合部)の粘膜に傷がないかを調べます。ただし、胃食道逆流症の患者さんの半数以上では、目に見える粘膜の傷は見つからないため、胃カメラだけでこの病気を確定することはできません。
胃カメラでは次のような点を確認することが重要です。
・萎縮性胃炎=慢性胃炎の有無を見る
→萎縮性胃炎がない人(ピロリ菌に感染していないと考えられる人)は、胃酸が多く分泌されていることが多いため、胃食道逆流症の可能性が高いと考えることができます。このように、胃カメラの結果は診断の大きな参考になります。
→萎縮性胃炎がない人(ピロリ菌に感染していないと考えられる人)は、胃酸が多く分泌されていることが多いため、胃食道逆流症の可能性が高いと考えることができます。このように、胃カメラの結果は診断の大きな参考になります。
※当院の胃カメラについて詳しくはこちら
その他の検査
必要に応じて、他の検査も行います
胃食道逆流症と似たような症状を起こす他の病気がないかを調べるため、次のような検査を行うこともあります。
・腹部エコー検査(腹部超音波検査)
・CT検査(コンピューター断層撮影)
・大腸カメラ(大腸内視鏡検査)
・小腸カプセル内視鏡検査(小さなカメラを内蔵したカプセルを飲みこむ検査)
・CT検査(コンピューター断層撮影)
・大腸カメラ(大腸内視鏡検査)
・小腸カプセル内視鏡検査(小さなカメラを内蔵したカプセルを飲みこむ検査)
これらの検査は、必要に応じて行い、GERD以外の病気が原因でないかを確認します(=他の病気を否定します)。
「胃酸を抑える薬」で症状が改善するかを確認します
胃食道逆流症が疑われる場合、まず「胃酸の分泌を抑える薬」を使ってみることがあります。この薬を使って、症状がよくなるかどうか経過を見ることで、GERDの可能性が高いかどうかを判断する材料になります。経過をみていくことはむしろ検査より診断に重要です。
詳しく調べたいときは「特殊な検査」も考えます
症状はあるのに、原因がはっきりしないときや、診断が難しい場合には、次のような特別な検査を行うこともあります。
・24時間食道pH(ピーエイチ)測定検査・インピーダンス検査
→食道の中に胃酸が逆流していないか、どれくらいの時間、どの程度の頻度で起こっているかを詳しく調べます。
・食道内圧測定検査
→食道の動きや圧力の状態を確認し、正常に働いているかを調べる検査です。
→食道の中に胃酸が逆流していないか、どれくらいの時間、どの程度の頻度で起こっているかを詳しく調べます。
・食道内圧測定検査
→食道の動きや圧力の状態を確認し、正常に働いているかを調べる検査です。
これらの検査は、専門的ですが、原因を詳しく調べるために必要になることがあります。
間違えやすい病気を慎重に除外(ちょっと似た他の病気がないか確認)
胃食道逆流症と似たような症状が出る病気がいくつかあります。これらの病気では治療の方法も異なるため、慎重に区別する(=鑑別する)必要があります。
・感染性食道炎
・食道がん
・放射線による食道炎(放射性食道炎)
・クローン病(腸の炎症性疾患)
・食道の動きの異常(食道運動異常症)
・好酸球性食道炎
・アカラシア(食道の筋肉がうまく動かなくなる病気)
・機能性ディスペプシア(胃の不快感があるが、検査で異常が見つからない状態)
・食道がん
・放射線による食道炎(放射性食道炎)
・クローン病(腸の炎症性疾患)
・食道の動きの異常(食道運動異常症)
・好酸球性食道炎
・アカラシア(食道の筋肉がうまく動かなくなる病気)
・機能性ディスペプシア(胃の不快感があるが、検査で異常が見つからない状態)
これらの病気と区別することも、胃食道逆流症の正確な診断にはとても大切です。
このように、胃食道逆流症の診断では、症状の聞き取りから始まり、胃カメラや薬の効果、必要に応じて専門的な検査まで、さまざまな方法を使って、総合的に判断していきます。正確な診断が、その後の治療の第一歩になります。
胃食道逆流症の治療について
GERDの治療は、主に薬による治療と生活習慣の見直しが中心です。症状の強さや、薬が効くかどうかに応じて治療方法が変わります。
薬による治療(薬物療法)
まずは、胃酸の分泌を抑える薬を使って、症状の改善を目指します。代表的な薬には、次のような種類があります。
プロトンポンプ阻害薬(PPI)
→胃酸の分泌を強力に抑える薬で、胃食道逆流症の治療でよく使われます。
カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB:ピーキャブ)
→PPIと同じく、胃酸の分泌を抑える薬ですが、より早く効果が出るとされています。
ヒスタミンH2受容体拮抗薬(H2ブロッカー)
→胃酸の分泌を抑える作用があり、PPIよりやや穏やかですが、補助的に使われることがあります。
→胃酸の分泌を強力に抑える薬で、胃食道逆流症の治療でよく使われます。
カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB:ピーキャブ)
→PPIと同じく、胃酸の分泌を抑える薬ですが、より早く効果が出るとされています。
ヒスタミンH2受容体拮抗薬(H2ブロッカー)
→胃酸の分泌を抑える作用があり、PPIよりやや穏やかですが、補助的に使われることがあります。
必要に応じて、以下のような工夫も行います。
・薬を1日2回に分けて使う(分割処方、必ずしも保険適応ではありません)
・通常よりも多めの量にして使う(倍量処方、必ずしも保険適応ではありません)
・胃の動きを助ける薬(胃運動促進薬)を追加する
これらは、症状がしっかり改善しない場合に検討される方法です。
・薬を1日2回に分けて使う(分割処方、必ずしも保険適応ではありません)
・通常よりも多めの量にして使う(倍量処方、必ずしも保険適応ではありません)
・胃の動きを助ける薬(胃運動促進薬)を追加する
これらは、症状がしっかり改善しない場合に検討される方法です。
薬で治りにくい場合の治療(その他の治療)
薬を使っても症状がなかなかよくならない場合、「薬が効きにくい胃食道逆流症」や「治りにくいタイプの胃食道逆流症(難治性)」とされ、次のような特別な治療が選ばれることもあります。
内視鏡を使った逆流防止の治療(内視鏡的逆流防止粘膜切除術)
→内視鏡を使って食道と胃の境目の粘膜の一部を切除し、逆流を防ぎやすくする方法です。
お腹に小さな穴をあけて手術をする方法(腹腔鏡下ニッセン手術)
→胃の入り口をしめる力を強くして、胃酸の逆流を防ぐための手術です。
→内視鏡を使って食道と胃の境目の粘膜の一部を切除し、逆流を防ぎやすくする方法です。
お腹に小さな穴をあけて手術をする方法(腹腔鏡下ニッセン手術)
→胃の入り口をしめる力を強くして、胃酸の逆流を防ぐための手術です。
このような方法は、専門の医師が患者さんの状態をしっかり確認したうえで検討されます。
日常生活や食事に関するアドバイス(生活・食事指導)
薬と同じくらい大切なのが、生活習慣や食事の見直しです。以下のようなことに気をつけることで、症状の改善につながります。
・体重を減らす
・寝るときは頭を少し高くして寝る
・背中が丸まらないように注意し、体幹を保つ
・お酒の量を減らす
・胃酸の逆流を起こしやすい食品を避ける
・寝る前3時間は何も食べないようにする
・食後すぐに激しい運動はしない
→お腹まわりに脂肪が多いと、胃酸が逆流しやすくなるためです。
→胃酸が上に逆流しにくくなります。
→姿勢が悪いと、お腹に圧力がかかりやすくなります。
・食べすぎないようにする
・よくかんで、ゆっくり食べる
・脂っこい食事を控える・お酒の量を減らす
・甘いものをとりすぎないようにする
→たとえば、チョコレート、炭酸飲料、トマト、ミントなどは症状を悪化させることがあります。牛乳は、逆に症状をやわらげる働きがある場合もあります。
→食後すぐに寝ると、胃酸が逆流しやすくなります。
→特に食後すぐの腹筋運動や激しい動きは逆流を悪化させることがあります。ただし、食事と食事の間に適度な運動をすることは、逆流を抑えるのに良い影響があります。
・症状の悪化する傾向のある状況を自分なりに分析を行う。
→(一般的にストレスのかかる状況が多い)分析ができたら、症状を悪化させる状況をなるべく避けるようにするこういった対応は場合によっては薬による治療より有効となります。(一種の行動認知療法)
このように、胃食道逆流症の治療では、薬だけでなく、日常生活の改善もとても重要です。自分に合った方法を医師と一緒に見つけ、無理のないペースで治療を進めることが大切です。
胃食道逆流症についてよくある質問(FAQ)
- 胃食道逆流症って、どんな病気ですか?
- 胃の中の主に酸(胃酸)が、食道に逆流してしまうことで、胸やけやのどの違和感などの症状が出る病気です。食道の粘膜が傷つくこともあり、その場合は「逆流性食道炎」と呼ばれます。
- 逆流性食道炎と胃食道逆流症はどう違うの?
- 逆流性食道炎は、胃酸が逆流して食道の粘膜に傷(炎症)ができた状態のことです。胃食道逆流症は、逆流による症状がある人すべてを含む広い言葉で、逆流性食道炎もその中に含まれます。
- どうしてこの病気になるのですか?
- 食生活の乱れ(脂っこいものや甘いものの取りすぎ)、肥満、ストレス、加齢、ピロリ菌の除菌後などが原因で、胃酸が多く出たり、胃の内容物が食道に逆流しやすくなったりすることで起こります。
- どんな症状があれば胃食道逆流症の可能性がありますか?
- 主な症状は、胸やけ、酸っぱいものがこみ上げる感じ(呑酸)、みぞおちの痛み、のどの違和感、せき、声のかすれ、眠りにくいなどです。これらが続く場合は医療機関の受診をおすすめします。
- 診断はどのように行いますか?
- まずは医師による問診で症状を確認します。必要に応じて、胃カメラ(内視鏡)などの検査を行って、食道の傷や胃の状態を確認します。また、薬の効き具合を見ることも診断の参考になります。
- 治療はどんなことをするのですか?
- 主に「胃酸を抑える薬」で治療します。プロトンポンプ阻害薬(PPI)や、カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)などが使われます。加えて、食生活の改善や姿勢の工夫なども大切です。
- 薬を飲めばすぐに治りますか?
- 薬を飲むことで多くの方は症状が改善しますが、個人差があります。数週間〜数ヶ月かかることもありますし、薬が効きにくい「難治性」のケースもあります。医師の指示に従って継続的に治療を受けることが大切です。
- 治ったら薬はやめていいの?再発はしない?
- 症状が落ち着いたあとも、再発することがあります。特に生活習慣が元に戻ると再発しやすいので、医師と相談しながら、薬の減量や中止のタイミングを決めていきます。
- 食事で気をつけることはありますか?
- 脂っこい食事、甘いもの、炭酸飲料、チョコレート、カフェイン、お酒などは控えめにしましょう。また、食べすぎ、早食い、寝る前3時間以内の食事も避けるようにしましょう。
- 手術が必要になることもありますか?
- ごく一部の方で、薬が効かない場合や、日常生活に強く支障がある場合には、内視鏡治療や手術(ニッセン手術)を行うことがあります。ただし、多くの方は薬と生活改善でコントロールできます。
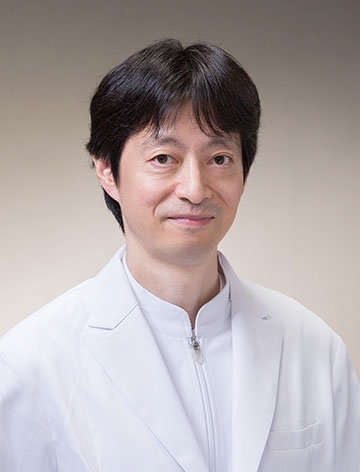
城北すずき内科クリニック
院長鈴木 恒治(すずき こうじ)
- 日本内科学会認定内科医
- 日本消化器病学会
- 日本消化器内視鏡学会専門医
- 日本カプセル内視鏡学会認定医