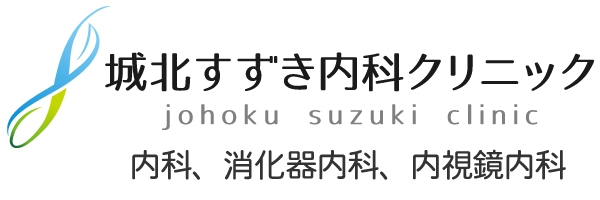潰瘍性大腸炎 ibd-uc
潰瘍性大腸炎とは?
疫学的特徴
病態と原因
発症原因は完全に明らかになっていないものの、遺伝的要因および環境的要因が関連し、免疫異常を起こし、腸管免疫が崩れ、慢性粘膜炎症を来すと考えられています。
炎症はほぼ粘膜に限局してみられ、びらん・潰瘍を慢性に形成します。多くの症例で直腸から炎症が起こり、連続性に上行していく経過をたどります。炎症部位が非連続性に見られる非典型例もあります。
慢性炎症継続症例では大腸癌発生率の上昇(炎症性発癌)がみられますが、生命予後(これからの暮らしや体調の見込み)は健常者と差はありません。
潰瘍性大腸炎の診断
問診と病歴聴取
問診、病歴聴取が最も重要です。慢性に持続する下痢(特に夜間睡眠中の下痢)、粘液便、血便、便意逼迫などを主訴とする場合、潰瘍性大腸炎を想起し疑います。
鑑別診断
次に鑑別診断として以下の疾患等を考え、否定していきます。
・感染性腸炎
・クローン病
・放射性腸炎
・薬剤性腸炎
(CD関連腸炎、非ステロイド抗炎症薬(NSAIDs)起因性腸炎、collagenous腸炎)
・虚血性腸炎
・腸管ベーチェット病
・膠原病関連性腸炎
・好酸球性胃腸炎
・GVHD腸炎
・腸管アミロイドーシス
・家族性地中海熱など
・感染性腸炎
・クローン病
・放射性腸炎
・薬剤性腸炎
(CD関連腸炎、非ステロイド抗炎症薬(NSAIDs)起因性腸炎、collagenous腸炎)
・虚血性腸炎
・腸管ベーチェット病
・膠原病関連性腸炎
・好酸球性胃腸炎
・GVHD腸炎
・腸管アミロイドーシス
・家族性地中海熱など
診断精度向上のための手順について
上記疾患を否定し、診断精度を上げるために下記手順を適宜追加していきます。
・生食の有無、基礎疾患の有無、薬剤服用歴(抗菌薬、胃酸分泌抑制薬など)、海外渡航歴の有無など聴取
・身体所見:貧血の有無、脱水の有無、全身状態、栄養状態、皮膚病変の有無、関節炎の有無などを診察にて把握しますが、特異的所見は必ずしもありません
・必要に応じ、眼科、整形外科、皮膚科受診を考慮(合併症の確認)
・生食の有無、基礎疾患の有無、薬剤服用歴(抗菌薬、胃酸分泌抑制薬など)、海外渡航歴の有無など聴取
・身体所見:貧血の有無、脱水の有無、全身状態、栄養状態、皮膚病変の有無、関節炎の有無などを診察にて把握しますが、特異的所見は必ずしもありません
・必要に応じ、眼科、整形外科、皮膚科受診を考慮(合併症の確認)
検査
まずは、下部消化管内視鏡(CS)を最優先に行い、直腸から連続性に上行する活動性粘膜炎症所見を認めれば潰瘍性大腸炎の可能性が高いと判断します。炎症部位があれば適宜生検を行います(生検にて確定診断とはならない場合が多く、各種所見を総合して判断を行います)。
他疾患否定のため、必要に応じ、便培養検査、血液検査、上部消化管内視鏡検査、CT検査、小腸カプセル内視鏡検査などの検査追加を適宜考慮します。
粘膜炎症高度症例では下部消化管内視鏡(CS)施行が疼痛のため困難な場合もあり、まずはS状結腸鏡である程度の判定・判断を行います。また、小腸通過時間が短い傾向のある潰瘍性大腸炎では大腸カプセル内視鏡が比較的低負担で行える場合もあり、深部大腸の情報把握を大腸カプセル内視鏡検査で行う考え方もとりうるでしょう。
他疾患否定のため、必要に応じ、便培養検査、血液検査、上部消化管内視鏡検査、CT検査、小腸カプセル内視鏡検査などの検査追加を適宜考慮します。
粘膜炎症高度症例では下部消化管内視鏡(CS)施行が疼痛のため困難な場合もあり、まずはS状結腸鏡である程度の判定・判断を行います。また、小腸通過時間が短い傾向のある潰瘍性大腸炎では大腸カプセル内視鏡が比較的低負担で行える場合もあり、深部大腸の情報把握を大腸カプセル内視鏡検査で行う考え方もとりうるでしょう。
潰瘍性大腸炎の治療方針の決定
治療方針は以下の分類を参考に決定します。
・臨床的重症度(排便回数、顕血便、発熱、頻脈、貧血の有無、血液炎症反応程度などで重症、中等症、軽症に分類)
・病型分類(全大腸型、左側大腸炎型、直腸炎型、区域性大腸炎型)
・活動期内視鏡所見分類
潰瘍性大腸炎の治療指針に沿い、まずは外科的緊急治療の必要性の有無を判断します。必要がない場合は、重症度に応じ、数ある治療薬の中から適切な薬剤を選択し、寛解導入療法を行います。
病状の安定が得られた場合、内視鏡的寛解、組織学的治癒などを治療目標として(treat to target)、局面局面で適切な薬剤を選択し、外科的治療回避、臨床的寛解維持、大腸癌発生リスク軽減など長期的予後改善を期した寛解維持療法を基本的には生涯にわたり継続していきます。
・臨床的重症度(排便回数、顕血便、発熱、頻脈、貧血の有無、血液炎症反応程度などで重症、中等症、軽症に分類)
・病型分類(全大腸型、左側大腸炎型、直腸炎型、区域性大腸炎型)
・活動期内視鏡所見分類
潰瘍性大腸炎の治療指針に沿い、まずは外科的緊急治療の必要性の有無を判断します。必要がない場合は、重症度に応じ、数ある治療薬の中から適切な薬剤を選択し、寛解導入療法を行います。
病状の安定が得られた場合、内視鏡的寛解、組織学的治癒などを治療目標として(treat to target)、局面局面で適切な薬剤を選択し、外科的治療回避、臨床的寛解維持、大腸癌発生リスク軽減など長期的予後改善を期した寛解維持療法を基本的には生涯にわたり継続していきます。
潰瘍性大腸炎の治療
寛解導入療法
軽症~中等症
5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA)の内服ないし局所製剤使用、および内服・局所製剤併用が基本治療となります。近年は、5-ASAを十分な高用量で使用することが重要とされています。1日1回内服とすることによりアドヒアランス向上が期待できます。一方、近年5-ASA製剤不耐例も増加しており注意が必要です。
・5-ASA内服薬:薬剤成分を炎症部位へ可及的に高濃度で届けるドラッグデリバリーの観点からいくつか種類があり、症例に応じて選択を行います
・局所製剤:5-ASA坐剤、注腸剤、ステロイド坐剤、注腸剤、ブデソニド注腸フォームなどあり、症例に応じ選択を行います
・局所製剤:5-ASA坐剤、注腸剤、ステロイド坐剤、注腸剤、ブデソニド注腸フォームなどあり、症例に応じ選択を行います
中等症~重症
5-ASA製剤にて改善が見られないないしは効果が不十分の場合、以下の治療を考慮します。
・ブデソニド内服薬(局所ステロイド作用が期待される薬剤、効果はステロイドに劣るが、副作用は少ない。8週間をめどに効果判定を行う)
・ステロイド内服薬(30~40mg/body使用する。長期的には不可逆的副作用も見られるため、2週間ほどで効果を判定し、3ヶ月をめどに内服終了を考慮する)
・ステロイド依存例・離脱困難例ではチオプリン製剤(アザチオプリン、6-メルカプトプリンなど)の追加を考慮する。チオプリン製剤使用時、事前にNUDT15遺伝子型の確認を行う
・カロテグラストメチル内服薬(免疫調整剤:8週間めどに効果評価を行う。投与期間は6ヶ月以内(8週間後の再処方可)。内服錠数が多いという難点がある)
・オザニモド塩酸塩内服薬ないしエトラシモドL-アルギニン内服薬(免疫調整剤:内服錠数は少ない。1日1回内服)
・ステロイド内服薬(30~40mg/body使用する。長期的には不可逆的副作用も見られるため、2週間ほどで効果を判定し、3ヶ月をめどに内服終了を考慮する)
・ステロイド依存例・離脱困難例ではチオプリン製剤(アザチオプリン、6-メルカプトプリンなど)の追加を考慮する。チオプリン製剤使用時、事前にNUDT15遺伝子型の確認を行う
・カロテグラストメチル内服薬(免疫調整剤:8週間めどに効果評価を行う。投与期間は6ヶ月以内(8週間後の再処方可)。内服錠数が多いという難点がある)
・オザニモド塩酸塩内服薬ないしエトラシモドL-アルギニン内服薬(免疫調整剤:内服錠数は少ない。1日1回内服)
上記薬剤で効果不十分のとき
・血球成分除去療法の追加
・免疫抑制剤の追加
・ステロイド大量静注療法への変更などの考慮
ないし“advanced therapy”(先進的な治療)とされる以下の治療への変更を考慮します。
・インフリキシマブ静注
・アダリムマブ皮下注
・ゴリムマブ皮下注
・ベドリズマブ点滴静注ないし皮下注
・ウステキヌマブ点滴静注
・ミリキズマブ点滴静注
・グセルクマブ点滴静注
・トファシチニブ経口
・フィルゴチニブ経口
・ウパダシチニブ経口
・免疫抑制剤の追加
・ステロイド大量静注療法への変更などの考慮
ないし“advanced therapy”(先進的な治療)とされる以下の治療への変更を考慮します。
・インフリキシマブ静注
・アダリムマブ皮下注
・ゴリムマブ皮下注
・ベドリズマブ点滴静注ないし皮下注
・ウステキヌマブ点滴静注
・ミリキズマブ点滴静注
・グセルクマブ点滴静注
・トファシチニブ経口
・フィルゴチニブ経口
・ウパダシチニブ経口
重症~難治例、劇症
・ステロイド大量静注療法
・タクロリムス経口療法
・シクロスポリン持続静注療法
・インフリキシマブ静注など適宜考慮
・タクロリムス経口療法
・シクロスポリン持続静注療法
・インフリキシマブ静注など適宜考慮
上記で改善ない場合は、外科手術考慮となります。
大腸穿孔例、中毒性巨大結腸症、大腸癌合併例、大量出血例では外科手術の絶対的適応となります。標準術式は大腸全摘+回腸囊肛門吻合術ないし大腸全摘+回腸囊肛門管吻合術です。
※重症潰瘍性大腸炎では、クロストリジウムディフィシルやサイトメガロウイルス感染の可能性を考え検索し、必要時治療を追加します。免疫抑制剤使用時、HBV再活性化による重症肝炎発症の可能性があり、定期的HBV検査を行うことが必要です。また、結核併発の可能性も考慮され、適宜インターフェロンガンマ遊離試験、CTなどの施行も考えます。
寛解維持療法
非難治例
5-ASAにて寛解維持療法を行います。
難治例
5-ASA、免疫抑制剤(6-MP)、血球成分除去、インフリキシマブ、アダリムマブ、ゴリムマブ、ベドリズマブ、ウステキヌマブ、ミリキズマブ、グセルクマブ、トファシチニブ、フィルゴチニブ、ウパダシチニブなどで寛解維持を試みます。
※長期経過例では潰瘍性大腸炎関連癌発症の可能性があり、病状安定例でも定期的な大腸内視鏡検査施行が考慮されます。
“advanced therapy”として使用される各治療薬一覧
| 薬剤分類 | 作用機序 | 特徴 | 一般名 | 商品名 | 初期投与経路 | 維持投与経路(間隔) | 自己注射 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNF-α阻害薬 | 炎症に関与するTNF-αを中和して炎症を抑える。 | 使用症例が多く、評価が確立されている。抗体産生、効果減弱例がある。インフリキシマブは重症例。 | ①インフリキシマブ | レミケード | 点滴静注 | 点滴静注(6-8w) | ||
| ②アダリムマブ | ヒュミラ | 皮下注 | 皮下注(2w) | 可 | ||||
| ③ゴリムマブ | シンポニー | 皮下注 | 皮下注(2w) | 可 | ||||
| インテグリン阻害薬 | リンパ球は血管内から粘膜に移動し炎症を惹起する。インテグリンはリンパ球が血管内から粘膜に移動する足掛りとなる。本薬剤はこの足掛りを阻害しリンパ球の粘膜への移動を抑え、炎症効果を表す。 | 全身への副作用が比較的少ないとされ、安全性が高いといわれる。(内服剤のカログラストメチルは、全身性副作用防止のため投与期間は原則6か月。再投与可能) | ④ベドリズマブ | エンタイビオ | 点滴静注 | 点滴静注(8w)ないし皮下注(2w) | 可 | |
| ⑤カログラストメチル | カログラ | 内服(24錠/日) | 内服(24錠/日) | 可 | ||||
| IL-12/23阻害剤 | 炎症を惹起するサイトカインのIL-12/23両者を阻害し粘膜炎症を抑える。 | 安全性は高いとされる。投与間隔を長く設定できる。効果発現にやや時間を要する。 | ⑥ウステキヌマブ | ステラーラ | 点滴静注 | 皮下注(8-12w) | ||
| IL-23阻害剤 | 炎症を惹起するサイトカインのIL-23のみを阻害し粘膜炎症を抑える。 | 安全性は高い。投与間隔は4~12週間。 | ⑦リサンキズマブ | スキリージ | 点滴静注 | 皮下注(8w) | 維持療法中悪化にて点滴静注可能 | |
| ⑧ミリキズマブ | オンボー | 点滴静注 | 皮下注(4w) | 可 | 維持療法中悪化にて点滴静注可能 | |||
| ⑨グセルクマブ | トレムフィア | 点滴静注 | 皮下注(4-8w) | |||||
| S1P受容体調節剤 | リンパ球は粘膜炎症部で重要な働きをする。本剤はリンパ球を末梢リンパ装置にリンパ球を保持させる作用により、循環血中リンパ球を減少させ、炎症部へのリンパ球郵送を抑制させる。 | 内服剤。効果発現は比較的緩徐 。徐脈などの副作用がまれにみられる。 | ⑩オザニモド塩酸塩 | ゼポジア | 内服(1錠/日) | 内服(1錠/日) | ||
| ⑪エトラシモドL-アルギニン | ベルスピティ | 内服(1錠/日) | 内服(1錠/日) | |||||
| JAK阻害剤 | 炎症性サイトカインなどの信号を細胞内に伝達する働きを示すヤヌスキナーゼ(JAK)を阻害し、複数の炎症経路を一気に抑制し、粘膜炎症を抑える。 | 効果発現が早く、作用も強いとされる。一方、全身免疫抑制効果は強く、感染症発現増加(帯状疱疹発生)、悪性腫瘍・血栓症発生などの可能性もありうる。 | ⑫トファシチニブクエン酸塩 | ゼルヤンツ | 内服(4錠/日) | 内服(2-4錠/日) | ||
| ⑬ウパダシチュニブ水和物 | リンボック | 内服(1錠/日) | 内服(1錠/日) | |||||
| ⑭フィルゴチニブマレイン酸塩 | ジセレカ | 内服(1錠/日) | 内服(1錠/日) |
薬剤選択目安
・重症度が高い場合
①、⑫、⑬、⑭などを考慮します(入院も考慮)。
・内服での治療を希望する場合
⑤、⑩、⑪(⑫、⑬、⑭)が選択肢となります。
・維持療法での自己注射を希望する場合
注射で通院間隔を長くしたい方には、②、③、④、⑧が適しています。
・自己注射以外の注射で通院間隔を長くしたい場合
①、④、⑥、⑦、⑨が選択肢となります。
・副作用の心配が低い薬剤
④、⑥、⑦、⑧、⑨などが該当します。
①、⑫、⑬、⑭などを考慮します(入院も考慮)。
・内服での治療を希望する場合
⑤、⑩、⑪(⑫、⑬、⑭)が選択肢となります。
・維持療法での自己注射を希望する場合
注射で通院間隔を長くしたい方には、②、③、④、⑧が適しています。
・自己注射以外の注射で通院間隔を長くしたい場合
①、④、⑥、⑦、⑨が選択肢となります。
・副作用の心配が低い薬剤
④、⑥、⑦、⑧、⑨などが該当します。
これらの目安を参考に、主治医と相談し薬剤を決定していきます。
難病医療費助成について
潰瘍性大腸炎は、厚生労働省が指定する難病の一つであり、医療費助成の対象となります。潰瘍性大腸炎と診断された場合、一定の条件を満たせば、医療費の自己負担が軽減される制度を利用できます。申請には指定された医療機関での診断書が必要で、山形市の自治体でも対応が可能です。詳細は、クリニックのスタッフまでお問い合わせください。
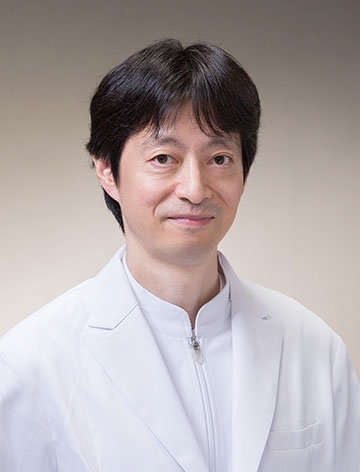
城北すずき内科クリニック
院長鈴木 恒治(すずき こうじ)
- 日本内科学会認定内科医
- 日本消化器病学会
- 日本消化器内視鏡学会専門医
- 日本カプセル内視鏡学会認定医