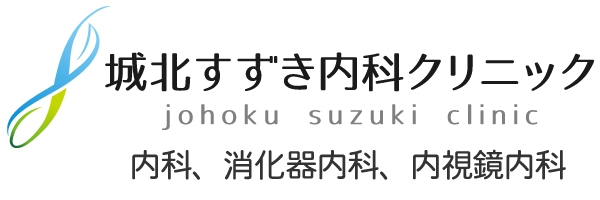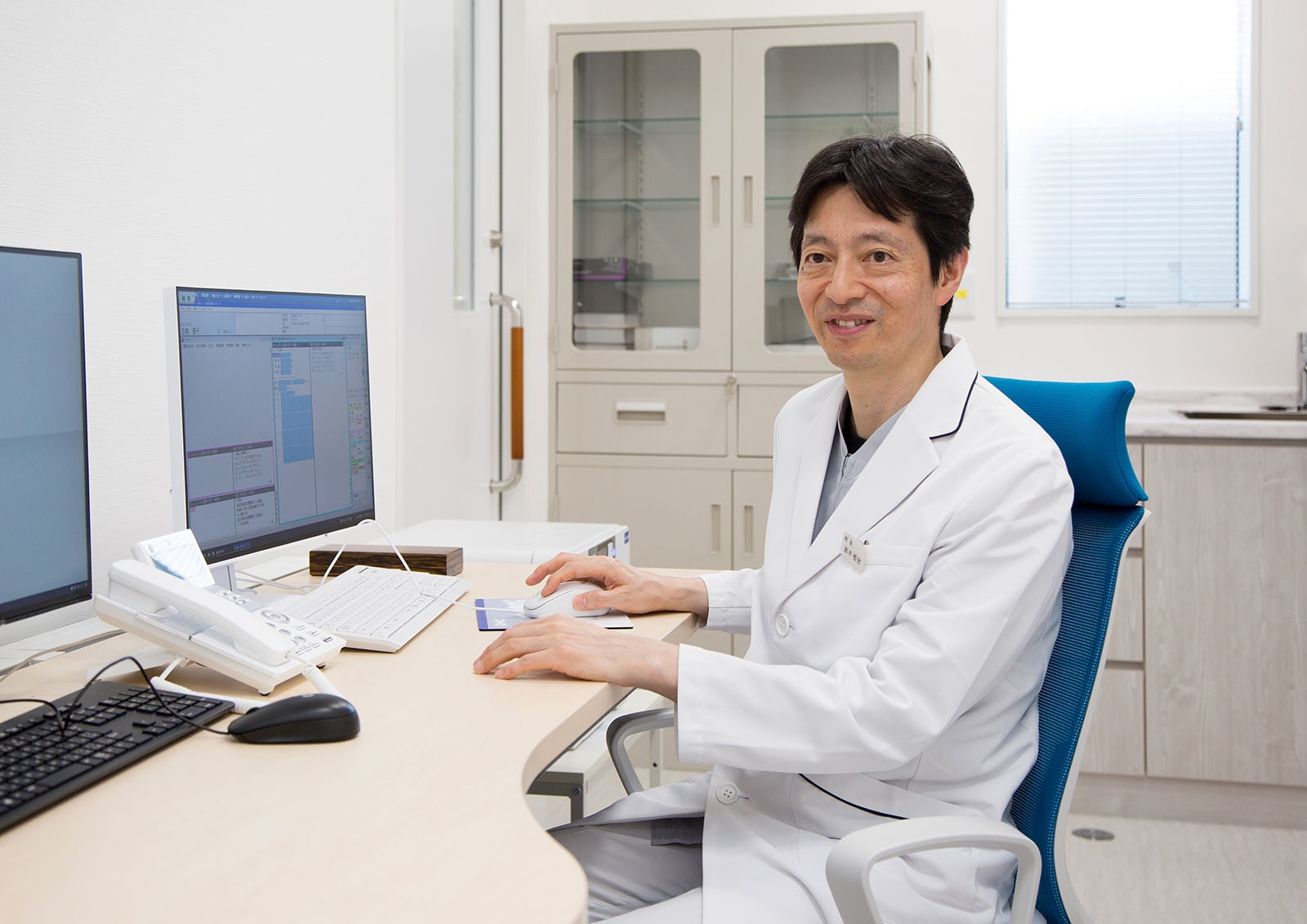過敏性腸症候群 ibs
過敏性腸症候群とは
口から肛門までの消化管に内視鏡などの検査で器質的な異常を認めないにもかかわらず、腹痛、腹満感、便秘、下痢などの慢性的消化器症状が、消化管運動障害を原因として引き起こされていると推定される病態を総称して機能性消化管障害(functional gastrointestinal disorders; FGID)と呼ばれます。胃食道逆流症(GERD)、機能性ディスペプシア(FD)、過敏性腸症候群(IBS)などが代表です。
IBSは、腹痛や下痢、便秘などの排便異常などの症状が半年以上慢性的に続く病態です。
原因は必ずしも明らかではありませんが、精神的ストレスや生活習慣が影響することが多いと考えられています。にストレスが強くなることにより小腸・大腸が知覚過敏となり機能低下をきたし症状が悪化するメカニズムが考えられています。命にかかわる病気である場合は少なく、適切な治療、生活指導で症状を緩和することが可能です。
IBSは、腹痛や下痢、便秘などの排便異常などの症状が半年以上慢性的に続く病態です。
原因は必ずしも明らかではありませんが、精神的ストレスや生活習慣が影響することが多いと考えられています。にストレスが強くなることにより小腸・大腸が知覚過敏となり機能低下をきたし症状が悪化するメカニズムが考えられています。命にかかわる病気である場合は少なく、適切な治療、生活指導で症状を緩和することが可能です。
過敏性腸症候群の原因
過敏性腸症候群の正確な原因は完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関連していると考えられています。
ストレス
心理的なストレスが消化管の運動や感覚を過敏にさせ、症状を引き起こすことがあります。
生活環境
不規則な食事や特定の食べ物が消化管に刺激を与え、便通の異常を引き起こすことがあります。
腸内フローラの異常
腸内にいる細菌のバランスが崩れると、消化機能が乱れることがあり、これが過敏性腸症候群に影響すると考えられています。
過敏体質
腸が通常の刺激に対して過敏に反応し、痛みや不快感を感じやすくなることがあります。
過敏性腸症候群の症状
腹痛
特に食後に腹痛が発生し、排便後に軽減することが多い。
下痢または便秘
頻繁な下痢や、反対に便秘が続く場合があります。一部の患者さんは下痢と便秘が交互に現れることもあります。
お腹の張り
腹部膨満感やガスがたまりやすい感覚があります。
粘液便・血便
一部の患者さんでは、便に白っぽい粘液や血液が混ざることがあります
過敏性腸症候群の診断方法
過敏性腸症候群の診断は、主に症状と病歴に基づいて行い、他の消化器系疾患と区別するために、検査を加え診断精度を上げる必要があります
問診
便検査
感染症や炎症性腸疾患の有無を確認するために、便の検査(潜血検査、培養検査)が行われることがあります。
血液・尿検査
貧血や炎症、感染症の兆候がないかを確認します。
エコー検査、CT検査
他臓器の疾患を否定するために必要となります。
内視鏡検査
症状に応じて上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)、下部消化菅内視鏡検査(大腸カメラ)ないし大腸カプセル内視鏡検査、小腸カプセル内視鏡検査を行い、消化菅の器質的疾患が存在しないことを確認することにより、過敏性腸症候群である可能性が高いと診断精度を より上げることが可能になります。
当院の内視鏡検査はこちらから
過敏性腸症候群の治療方法
過敏性腸症候群の治療は、主に症状の緩和と日常生活の改善に焦点を当てています。
薬物療法
腹痛や下痢、便秘の症状に応じて、消化管の運動を調整する薬や、腸内環境を改善する整腸剤が処方することがあります。
食事療法
消化しにくい炭水化物を避ける食事や、脂肪分の少ない食事が有効とされています。また、食物繊維の摂取量を調整することで便通を改善する場合もあります
心理療法
ストレス管理が症状の改善につながるため、認知行動療法やストレスコントロールのためのカウンセリングや抗不安薬の処方などをおすすめすることがあります。
生活習慣の改善
規則正しい生活を送り、適度な運動や十分な睡眠を確保することも重要です。
過敏性腸症候群について自宅できること
過敏性腸症候群の症状を和らげるために、自宅でできる対策もいくつかあります。
ストレス管理
リラックスする時間を作り、過度なストレスを避けることが重要です。ヨガなどのリラクゼーション法も効果的です。
食事の見直し
食事内容に気を配り、炭水化物を減量し、脂肪分の多い食品や刺激物を避けることが推奨されます。また、少量の食事を数回に分けて摂取することで、消化管に負担をかけないようにしましょう。
水分摂取
適度な水分補給は、便秘を防ぎ、腸内の動きをスムーズにします。
適度な運動
ウォーキングなどの軽い運動が、腸の働きを活性化させ、症状の改善に役立ちます。
腹式呼吸法
眠前などに鼻からゆっくりおなかを膨らませながら息を吸い、1-2秒息を止め、ゆっくり口から息を吐く腹式呼吸法を15分程度行うことは、副交感神経優位に自律神経系を調整する効果があり、ストレス緩和により腹部症状緩和に繋がります。
過敏性腸症候群についてよくある質問
- 過敏性腸症候群は治りますか?
- 過敏性腸症候群は完全に治るわけではありませんが、適切な治療と生活習慣の改善によって症状を管理することが可能です。
- ストレスが原因で症状が悪化しますか?
- はい。ストレスは過敏性腸症候群の主な悪化要因の一つです。ストレス管理を心がけることで、症状のコントロールがしやすくなります。
- 過敏性腸症候群は命に関わる病気ですか?
- いいえ。過敏性腸症候群は命に関わる病気ではありませんが、放置するとクローン病など1段階重い病態に移行していくケースも経験され、日常生活の質に大きな影響を与える可能性もあります。早期から適切な治療で症状を緩和することが重要です。
- 食べ物で症状を抑えることはできますか?
- はい。低FODMAP(小腸で吸収されにくい発酵性糖質※)食や食物繊維の摂取量を調整することで、症状の緩和が期待できます。医師や栄養士に相談しながら、自分に合った食事を見つけることが大切です。
- 過敏性腸症候群の治療にはどれくらいの時間がかかりますか?
- 個人差がありますが、生活習慣の改善や治療を始めてから数週間から数カ月で症状が改善することが多いです。治療中断にて容易に再発することが多いため、長期的に長く付き合っていく意識をもつことが求められます。
※参考:
高FODMAP食品(なるべく多くは摂取しない方がいいとされる)
O;ガラクトオリゴ糖:納豆、絹ごし豆腐
O;フルクタン:小麦、たまねぎなど
O;ラクトース:牛乳、ヨーグルト、アイスクリームなど動物性乳製品
M;フルクトース:果物や野菜(りんご、アスパラガスなど)やハチミツなど
P;マンニトール:キノコルイ、カリフラワー、さやえんどうなど
P;ソルビトール:りんご、なし、プラムなど
P;キシリトール:シュガーレス菓子など
一般的に体にいいといわれているものが多く含まれます。制限しすぎると栄養不足になる可能性もあります。ゆっくり体調をみながら2~6週間かけて上記食品を減量し、その後体調をみながら改善があった場合2か月ほどかけて戻していく長期的な工程を考慮してください。体調が悪化した場合は無理に継続しないことも必要です。
高FODMAP食品(なるべく多くは摂取しない方がいいとされる)
O;ガラクトオリゴ糖:納豆、絹ごし豆腐
O;フルクタン:小麦、たまねぎなど
O;ラクトース:牛乳、ヨーグルト、アイスクリームなど動物性乳製品
M;フルクトース:果物や野菜(りんご、アスパラガスなど)やハチミツなど
P;マンニトール:キノコルイ、カリフラワー、さやえんどうなど
P;ソルビトール:りんご、なし、プラムなど
P;キシリトール:シュガーレス菓子など
一般的に体にいいといわれているものが多く含まれます。制限しすぎると栄養不足になる可能性もあります。ゆっくり体調をみながら2~6週間かけて上記食品を減量し、その後体調をみながら改善があった場合2か月ほどかけて戻していく長期的な工程を考慮してください。体調が悪化した場合は無理に継続しないことも必要です。
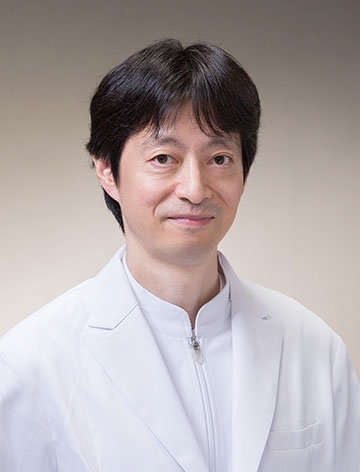
城北すずき内科クリニック
院長鈴木 恒治(すずき こうじ)
- 日本内科学会認定内科医
- 日本消化器病学会
- 日本消化器内視鏡学会専門医
- 日本カプセル内視鏡学会認定医