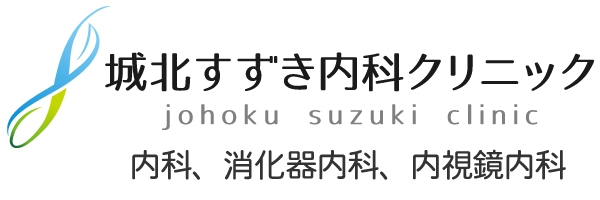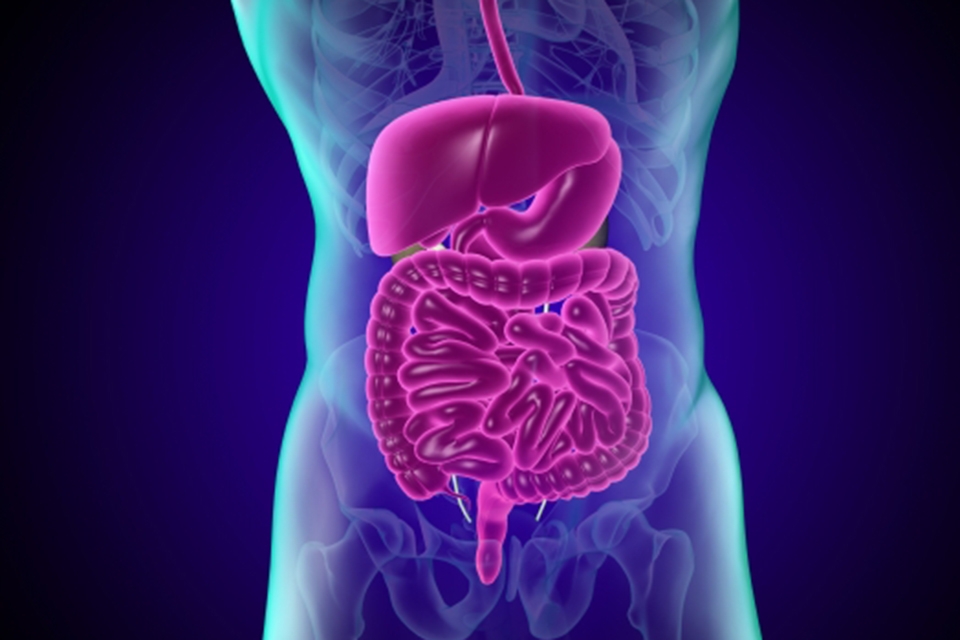クローン病 ibd-cd
クローン病(Crohn's disease;CD)とは?
クローン病の特徴
クローン病の症状
臨床像は病変部位や範囲により異なりますが、下痢や腹痛、肛門病変などの消化管症状と、発熱や体重減少、栄養障害など全身症状を認めます。貧血、関節炎、虹彩炎(目の炎症)、皮膚病変など腸管外合併症も多彩です。
クローン病の原因
原因は完全に明らかになってはいません。遺伝的因子と環境因子の関与による免疫異常(体を守る仕組みの異常)が主原因と考えられています。またクローン病の家族歴があることは発病のリスク因子となりえます。
クローン病の経過
クローン病の診断
問診と病歴聴取
鑑別診断
鑑別診断として以下のような疾患等を否定していきます。
・過敏性腸症候群
・大腸癌・悪性リンパ腫
・感染性腸炎
・潰瘍性大腸炎
・腸管ベーチェット病
・非特異性多発性小腸潰瘍
・NSAIDs潰瘍(痛み止めによる潰瘍)
・放射性腸炎など
※過敏性腸症候群など機能性腸疾患との鑑別に便中カルプロテクチン測定が有用な場合があります。
・過敏性腸症候群
・大腸癌・悪性リンパ腫
・感染性腸炎
・潰瘍性大腸炎
・腸管ベーチェット病
・非特異性多発性小腸潰瘍
・NSAIDs潰瘍(痛み止めによる潰瘍)
・放射性腸炎など
※過敏性腸症候群など機能性腸疾患との鑑別に便中カルプロテクチン測定が有用な場合があります。
初期の大腸型クローン病は区域性大腸炎型潰瘍性大腸炎との鑑別が困難な場合があり、その際はinflammatory bowel disease unclassified(IBDU:分類不能型炎症性腸疾患)としてフォローされます。
検査
まずは、採血、腹部エコー、レントゲン検査、便培養検査などを行います。
上部消化管内視鏡検査(EGD:胃カメラ)、下部消化管内視鏡(CS:大腸カメラ)、体幹部CT検査を行います。内視鏡検査にて病変を認める場合は積極的に生検検査(組織を採取して調べる検査)を行います。
必要時、上部消化管造影検査、注腸造影検査、小腸造影検査(バリウムを使った検査)の施行を考慮します。
各種検査やパテンシーカプセル(腸の狭さを調べるカプセル)などにて小腸狭窄の可能性が低い場合、小腸カプセル内視鏡検査の施行を考慮します。
場合により、バルーン小腸内視鏡検査、大腸カプセル内視鏡検査の必要性を勘案します。
施設によってはCTエンテログラフィー、MRエンテログラフィー検査(特殊な腸の画像検査)なども考慮されます。
痔瘻が疑われる場合は積極的に外科受診を考慮します。
施設によってはCTエンテログラフィー、MRエンテログラフィー検査(特殊な腸の画像検査)なども考慮されます。
痔瘻が疑われる場合は積極的に外科受診を考慮します。
必要に応じ、整形外科、皮膚科、眼科など他科受診を検討します。
早期発見は予後改善の観点からとても重要であり、若年者の体重減少を伴い、とくに肛門痛などの訴えを持つ慢性再発性腹痛患者に対し、腸管閉塞の有無を慎重に勘案した上での、早期の小腸カプセル内視鏡施行は、他検査にて発見できない小腸内早期病変を発見→診断・早期治療介入の可能性を生み、非常に意義深いものと考えられます。
上記の検査から消化管の特徴的内視鏡所見、生検病理診断などから、難治性炎症性腸管障害調査研究班によるクローン病診断基準により診断を行います。
クローン病の治療方針の決定
重症度分類(Crohn's disease activity index; CDAI:クローン病活動性指数)や病変範囲分類などから、外科手術適応の有無を判断し、適応がない場合は栄養療法ないし薬物療法、両者の併用による活動期の治療を症例に応じ選択していきます。
従来は、5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA)、ステロイド剤、ブデソニドなどの薬剤が初期に行われ、その後、5-ASA効果不十分時、advancedtherapy(先進治療)と称される下記の薬剤が使用される場合が定石でした。
・インフリキシマブ
・アダリムマブ
・ベドリズマブ
・ウステキヌマブ
・リサンキズマブ
・グセルクマブ
・ウパダシチニブ
・インフリキシマブ
・アダリムマブ
・ベドリズマブ
・ウステキヌマブ
・リサンキズマブ
・グセルクマブ
・ウパダシチニブ
近年は、特に予後不良が予測される症例に関しては、積極的にadvanced therapyを従来治療に先行して行う考え方も出てきています。
40歳未満症例、肛門病変あり症例、初回ステロイド治療例、喫煙者などは診断後5年における予後は不良とされ、より積極的な内科治療を選択すべきとされています。
寛解(症状が落ち着いた状態)が得られた場合、寛解維持療法を行います。
寛解(症状が落ち着いた状態)が得られた場合、寛解維持療法を行います。
クローン病の治療
活動期の治療
軽症~中等症
・5-ASA内服薬:CD治療に使用される基本薬剤です。
・ブデソニド内服薬:局所ステロイド作用が期待される薬剤で、効果はステロイドに劣りますが、副作用は少ないです。8週間をめどに効果判定を行います。
・ステロイド内服薬:30~40mg/body使用します。長期的には不可逆的副作用(元に戻らない副作用)も見られるため、2週間ほどで効果を判定し、寛解維持効果はなく、3ヶ月をめどに内服終了を考慮します。
・栄養療法
成分栄養剤(エレンタール®):粘膜刺激性は低いですが、やや飲みにくいです。
服用が困難な場合適宜、以下を選択。
消化態栄養剤(ツインライン®)
半消化態栄養剤(エンシュアH®など)
・ブデソニド内服薬:局所ステロイド作用が期待される薬剤で、効果はステロイドに劣りますが、副作用は少ないです。8週間をめどに効果判定を行います。
・ステロイド内服薬:30~40mg/body使用します。長期的には不可逆的副作用(元に戻らない副作用)も見られるため、2週間ほどで効果を判定し、寛解維持効果はなく、3ヶ月をめどに内服終了を考慮します。
・栄養療法
成分栄養剤(エレンタール®):粘膜刺激性は低いですが、やや飲みにくいです。
服用が困難な場合適宜、以下を選択。
消化態栄養剤(ツインライン®)
半消化態栄養剤(エンシュアH®など)
中等症~重症
・ステロイド内服~ステロイド静注(点滴)
・抗菌薬(メトロニダゾール®、シプロキサン®)
・インフリキシマブ:アザチオプリンとの併用が有用な場合が多いです。痔瘻患者にも有効性があります。
・アダリムマブ:インフリキシマブ効果減弱例に有用な場合もあります。
・ベドリズマブ:副作用頻度は低い特徴があります。
・ウステキヌマブ:副作用頻度は低い特徴があります。
・リサンキズマブ:副作用頻度は低い特徴があります。
・グセルクマブ:最も新しい薬剤です。
・ウパダシチニブ経口:JAK阻害剤(免疫を調整する薬)です。
・抗菌薬(メトロニダゾール®、シプロキサン®)
・ステロイド依存例・離脱困難例ではチオプリン製剤(アザチオプリン、6-メルカプトプリンなど)の追加を考慮します。チオプリン製剤使用時、事前にNUDT15遺伝子型の確認を行います。
※上記で効果不十分時、ないし予後不良予測例では早期から以下advanced therapy(先進治療)の導入をします。
・アダリムマブ:インフリキシマブ効果減弱例に有用な場合もあります。
・ベドリズマブ:副作用頻度は低い特徴があります。
・ウステキヌマブ:副作用頻度は低い特徴があります。
・リサンキズマブ:副作用頻度は低い特徴があります。
・グセルクマブ:最も新しい薬剤です。
・ウパダシチニブ経口:JAK阻害剤(免疫を調整する薬)です。
免疫抑制剤使用時、HBV(B型肝炎ウイルス)活性化に伴う重症肝炎発症の可能性があり、定期的HBVモニタリング(検査での監視)が必要とされます。
ステロイド3か月以上使用例は、眼科疾患・骨粗しょう症・精神疾患発症ほか副作用には十分留意する必要があります。
ステロイド3か月以上使用例は、眼科疾患・骨粗しょう症・精神疾患発症ほか副作用には十分留意する必要があります。
外科手術適応
腸閉塞(腸が詰まる)、穿孔(腸に穴が開く)、制御不能出血、癌合併などでは腸管切除を行います。
狭窄に対し、狭窄形成術などが行われます。(内視鏡的アプローチ可能時には内視鏡的バルーン拡張術が行われる場合もあります)
狭窄に対し、狭窄形成術などが行われます。(内視鏡的アプローチ可能時には内視鏡的バルーン拡張術が行われる場合もあります)
寛解維持療法
下記薬剤より適宜選択し継続治療を行います。
・5-ASA製剤
・免疫抑制剤
・advanced therapy
・インフリキシマブ
・アダリムマブ
・ベドリズマブ
・5-ASA製剤
・免疫抑制剤
・advanced therapy
・インフリキシマブ
・アダリムマブ
・ベドリズマブ
・ウステキヌマブ
・栄養療法
肛門部病変の治療
外科的治療として、ドレナージ(膿を出す処置)、シートン法(糸を通す治療)、肛門拡張術など適宜行います。
・必要時、抗菌薬(メトロニダゾール®、シプロキサン®)
・インフリキシマブ
・アダリムマブ
・ウステキヌマブなどを使用します。
・必要時、抗菌薬(メトロニダゾール®、シプロキサン®)
・インフリキシマブ
・アダリムマブ
・ウステキヌマブなどを使用します。
狭窄/瘻孔の治療
おもに外科的処置が行われる場合が多いです。
狭窄に対しては、内視鏡的処置が行われる場合も増加しています。
薬剤にての狭窄解除は通常難しいとされますが、advanced therapy継続にての狭窄解除例も経験されるようになっています。
狭窄に対しては、内視鏡的処置が行われる場合も増加しています。
薬剤にての狭窄解除は通常難しいとされますが、advanced therapy継続にての狭窄解除例も経験されるようになっています。
術後の再発治療
・5-ASA製剤
・免疫抑制剤
・インフリキシマブ、アダリムマブ
・栄養療法などが考慮されます。
・免疫抑制剤
・インフリキシマブ、アダリムマブ
・栄養療法などが考慮されます。
フォローアップ
寛解維持療法の中止で多くの患者で再燃(症状の悪化)するため、基本、治療は生涯にわたり、通院治療を継続します。
外科手術後患者でも10年後には術後累積再手術率が50%以上との報告があり、慎重な検査治療を継続していく必要があります。
長期経過例では消化管癌発生リスクは健常者より高く、定期的な内視鏡検査施行が推奨されます。
寛解状態でも3か月に1回程度の採血、および糞便中カルプロテクチン測定、血清ロイシンリッチαグリコプロテイン測定が推奨されます。
外科手術後患者でも10年後には術後累積再手術率が50%以上との報告があり、慎重な検査治療を継続していく必要があります。
長期経過例では消化管癌発生リスクは健常者より高く、定期的な内視鏡検査施行が推奨されます。
寛解状態でも3か月に1回程度の採血、および糞便中カルプロテクチン測定、血清ロイシンリッチαグリコプロテイン測定が推奨されます。
難病医療費助成について
クローン病は、厚生労働省が指定する難病の一つであり、医療費助成の対象となります。クローン病と診断された場合、一定の条件を満たせば、医療費の自己負担が軽減される制度を利用できます。申請には指定された医療機関での診断書が必要で、山形市の自治体でも対応が可能です。詳細は、クリニックのスタッフまでお問い合わせください。
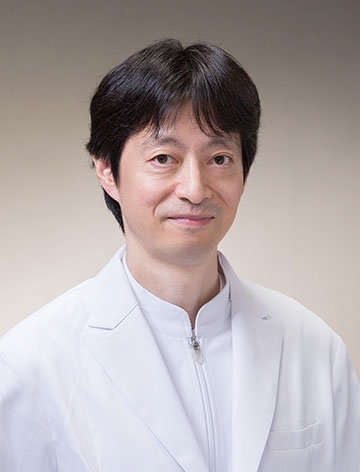
城北すずき内科クリニック
院長鈴木 恒治(すずき こうじ)
- 日本内科学会認定内科医
- 日本消化器病学会
- 日本消化器内視鏡学会専門医
- 日本カプセル内視鏡学会認定医